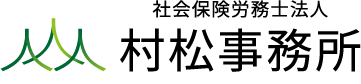立ち作業の負担軽減対策
◆立ち作業による体への負担
工場のライン作業や、工事現場における交通誘導作業、スーパーの会計作業など様々な場面で見られる「立ち作業」は、業務に集中しやすい、とっさに動きやすいといったメリットがある一方で、長時間持続的に行われると足腰等への負担が大きくなり、作業効率も落ちるといったデメリットもあります。従業員の負担を軽減するために、事業者として何ができるか、見てみましょう。
◆労働安全衛生規則の規定
まず、労働安全衛生規則615条では、就業中にしばしば座ることのできる機会のあるときには椅子の備え付けを事業者に義務付けています。
「(立業のためのいす)第615条 事業者は、持続的立業に従事する労働者が就業中しばしばすわることのできる機会のあるときは、当該労働者が利用することのできるいすを備えなければならない。」
必ずしも座って作業をすることを求めているものではありませんが、立ち作業にともなう従業員の足腰の負担を軽減するためには、作業時間の短縮やこまめな休憩の取得等を行うことや、作業中に座ることができるイスを設置するなどの対策が考えられます。
◆企業の取組事例
厚生労働省のホームページに、小売業、警備業、その他事業と産業ごとに各企業での「立ち作業の負担軽減対策の取組事例紹介」がされています。
【事例1】スーパーマーケットのレジ作業
軽く腰を掛けられるイスを設置し、接客の合間などに座っての待機を可能にした。レジの足元にクッション性のあるマットを設置。 レジ以外には、可動式の陳列棚の導入により、品出しの作業効率を上げるとともに、中腰姿勢の時間を削減。
【事例2】警備業
座ることで、疲労・ストレスの軽減、心拍数・血圧などの上昇の抑制、身体的な負担が軽減されるとの研究結果をもとに、座哨しての警備を実践。座哨警備を行う際には、事前に現場の責任者と話し合い、作業場所と警備の位置関係や交通量を確認、安全第一で実施。
その他、高さのないパンプスやスニーカーでの勤務を可能にすることで、立ち作業における足腰の負担軽減対策をしている例もあるようです。いずれの事例でも費用の目安は数万円でした。
【厚生労働省「立ち作業の負担軽減対策の取組事例紹介」】→サイトがありますので、ご覧ください。
新法施行前のフリーランス取引状況
~公正取引委員会・厚生労働省の 実態調査結果と必要な対応(厚労省関係)
フリーランスとして働く人々が安心して働ける環境を整備する目的で、11月1日に特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律(以下、「フリーランス法」)が施行されました。これを踏まえ、公正取引委員会と厚生労働省は共同で、新法施行前のフリーランス取引の実態を把握するために、様々な業界のフリーランス労働者と委託者を対象に、取引条件や契約内容、報酬の支払い状況などの実態調査を行いました。
◆調査結果の概要と必要な対応(=厚労省関係の育児介護等と業務の両立配慮とハラスメント対策の整備)
○フリーランス法の認知度
新法の内容をよく知らないと回答した委託者は54.5%、フリーランスは76.3%と、双方ともに認知度が低い結果が出ています。業種でみると、建設業と医療、福祉での認知度の低さが目立ちます。
○取引条件の明示
取引条件を明示しなかったことがある割合として、委託者は17.4%、フリーランスは44.6%と回答しており、いずれも建設業において多くみられます。
○買いたたき
報酬の額について十分な協議がなされていない割合として、委託者22.2%、フリーランス67.1%と大きく差がついており、フリーランスの不満の声が多く寄せられています。
○募集情報の表示
業務委託の募集広告内容と実際の業務内容に違いがあったとする割合は、委託者で2.6%、フリーランス53.1%と差が大きく、特に生活関連サービス業や娯楽業でフリーランスにとって掲載内容の誤りや誤解を生じさせる表示であったとの意見が多くありました。
○育児介護等と業務の両立配慮
妊娠・出産・育児・介護の事情に関して、業務との両立のため、委託者に配慮を求めたいフリーランスは70.7%に上ります。それに対し、応じていないと回答した委託者は0%で、フリーランスは6.8%が対応してもらえなかったと回答。
<育児介護等への配慮:6か月以上の業務委託については配慮義務があり、6か月未満の業務委託は配慮するように努める。>
(事例)
特定受託事業者(フリーランス)が、育児介護等の配慮に関すること(「①子の急病で入院したため、納期を延期してほしい。」「②介護のためオンラインでの業務に変更したい。」を、特定業務委託事業者(委託元)へ申し出る。
(実際の対応方法)
特定業務委託事業者(委託元)は、申出の内容等を把握し、取り得る選択肢を検討する。
(実際の対応事例)
①実施できる場合:納期を変更します。
⇒配慮の内容の伝達・実施
②やむを得ず実施できない場合:今回は作業が必要なので、オンラインへの変更は難しい。
⇒配慮不実施の伝達・理由説明
※申出があったとき、対応を講じることが必要で、検討した結果、上記のとおり、実際に配慮することができないことは法違反ではない。
○ハラスメント対策の整備
フリーランスへのハラスメント対策が整備・社内通知されていない委託者は51%と、体制整備の遅れが目立ちます。
(実際の対応方法)
特定業務委託事業者(委託元)が講ずべき措置(以下の主要3つ)として、自社の“職場のハラスメント対策”と同様に考える。また、相談者や行為者などのプライバシー保護と自社の従業員やフリーランスの方へ不利益な取扱いをしない旨を周知・啓発する必要があります。
(1)ハラスメントを行ってはならない旨の方針の明確化、方針の周知・啓発
(2)相談に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備(相談窓口の設置など)
(3)業務委託におけるハラスメントへの事後の迅速かつ適切な対応
以上、法施行前のフリーランスの労働環境は、生活が不安定になるリスクが多く、不満が募る状態となっていたことがわかります。新法の施行により、これらの問題が改善されることが期待されます。